
2022年3月24日
労働契約
退職勧奨と解雇は、何がどう違うのか?
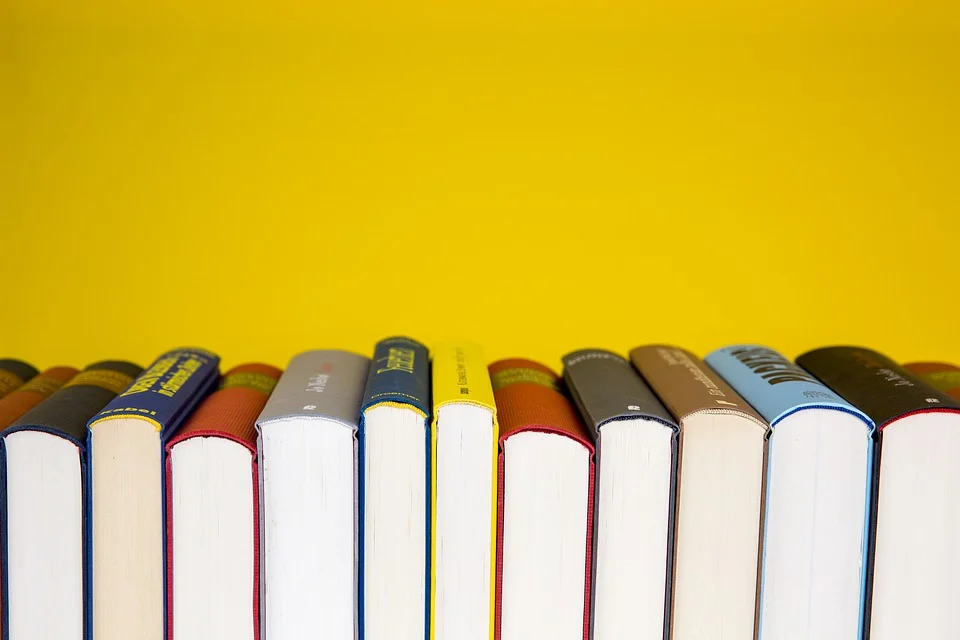
2022年3月24日
就業規則
就業規則の構成は、正社員に適用する社員就業規則を本則として、その一部分である賃金や退職金、育児・介護などに関する項目は条数が多くなるため別規程として定められています。同様にパートタイマーや嘱託社員など正社員と異なる雇用形態がある場合は、労働時間や給与などの労働条件も異なりますので、やはり別に作成します。
正社員と同一の就業規則の中に納めてしまうと、複雑で理解しづらかったり、誤解を生じてしまうおそれがあるからです。
そこで就業規則の作成や改訂にあたり、まず最初に検討すべきことはどの項目を別規程として定めるひつようがあるのか、何種類の雇用形態があって別に定めるべきかの区分になります。
特に後者の雇用形態については、契約期間の有無や休暇などの労働条件の相違点が明確に区分されていないケースが散見されますので、就業規則の作成(改訂)を通じて、この機会に整理することをお勧めします。
労働条件の相違点が区分できたら、その内容を就業規則に落とし込みます。最後に「本規則に定めのない事項は、社員就業規則を適用する」と加えることで、社員就業規則との違いを明らかにすることができます。
本稿では雇用形態別の労働条件の相違点を整理するポイントを解説します。
雇用形態によって採用選考の方法が異なるときは、雇用形態ごとに実施する面接試験、筆記試験、適性検査などを明記します。
通常、社員に代表される無期雇用契約は、企業側の雇用リスクの回避を目的として試用期間を設けています。一方、有期雇用契約では雇用のを設けて長期雇用のリスクを回避していますので、試用期間を設けて二重にリスク回避をする必要はありません。その代わりに契約更新と雇止めの条件に関する条文が必要になります。
労働時間や休日が統一化されていれば明記しますが、統一化できないときは、「別に定める雇用契約のとおり」と定めます。
労働条件のうち最も重要な項目となりますので、時給制や月給制などの賃金の支払い形態の違い、諸手当の種類と金額、賞与・退職金の有無を明確に区分する必要があります。
年次有給休暇や育児休業など法律で定められた休暇・休業制度は、法律を上回って付与する場合はその内容を、法律で義務化されていない任意の特別・休職制度などについては、雇用形態別の適用の有無や期間を明確にします。
<社員・パートタイム・嘱託職員の労働条件の相違点(例)>
| 雇用形態 項 目 | 社員 | パートタイマー | 嘱託社員 |
| 定義 | 期間の定めなく採用された者。 | 1日6時間・1週30時間以内。補助職 | 定年退職後、再雇用された者 |
| 試用期間 | 3ヵ月 | なし | なし |
| 期間の定め | なし | あり。1年契約 | あり。1年契約 |
| 異動・出向 | あり | なし | なし |
| 休職 | あり。最長1年 | なし | あり。最長6ヵ月 |
| 就業時間 | 9:00~18:00 | 個別契約 | 個別契約 |
| 休日 | 土・日、国民の祝日・休日、年末年始3日 | 個別契約 | 個別契約 |
| 年次有給休暇 | 法律どおり | 同左 | 同左 |
| 時間単位の年休 | あり | なし | あり |
| 年休積立制度 | あり | なし | あり |
| 特別休暇 | あり | なし | あり |
| 賃金形態 | 日給月給 | 時給制 | 月給制 |
| 昇給 | あり | あり | なし |
| 諸手当 | 役職手当、家族手当 住宅手当、通勤手当 | 通勤手当 | 通勤手当 |
| 賞与 | 6月と12月年2回 | なし | なし |
| 退職金 | 勤続2年以上あり | なし | |
| 慶弔見舞金 | あり | あり | あり |

TEL045-440-4777
FAX045-440-4888
営業時間:平日9:00~18:00(定休日・土日祝)